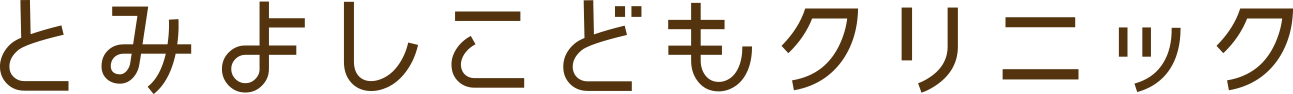発熱するきっかけで最も多いのが、風邪だと思います。その風邪をひくとさまざまな症状が出現します。咳・鼻水がでたり、喉が痛くなったり、場合によっては、発熱したりします。
その原因は多くの場合、かぜ症状を引き起こすウイルスが体の中に入り、攻撃してくるからです。では、ウイルスなどの攻撃を受けたとき、なぜ発熱するのでしょうか。
目次
1)発熱の定義

人の平熱は一般的には36.5℃±0.5と言われています。ただ小児の場合は、代謝が良いため多少高めです。
- 乳幼児 36.7℃~37.4℃
- 学童 36.5℃~37.4℃程度
個人差や、季節・環境・時間帯などによっても、影響が出やすくなります。そのため、何度くらいが平熱なのか日ごろから測っておくほうが良いかもしれません。
発熱の目安としては、(1)37.5℃以上 もしくは(2)平熱より1℃以上高い と考えて貰えば良いと思います。
2)発熱の仕組み
かぜの原因となるウイルスなどの外敵である病原微生物が侵入してくると、外敵に気づいた免疫細胞たちが一斉に動き出します。
その免疫細胞の働きのひとつに、味方への情報伝達があります。
それを受けて、体温調整の指令等の役割をしている脳の視床下部という部位が、体温を上げるよう指示を出します。
その指示に基づき、設定された体温になるよう皮膚の血管が収縮して熱放散を抑える反応が開始されたり、筋肉をふるえさせて熱の産生をうながします。
体温調節中枢の調節レベルが通常よりも高いところに設定された場合、初期段階では血液の温度は中枢の調節レベルよりも低いことになりますから、体温をその設定されたレベルまで引き上げようと、中枢は体熱の放散を減らし、反対に体熱産生を増やそうとします。その時に、体熱の放散量を急速に減少させるべく、皮膚血管の収縮、立毛筋の収縮などが起こります。それらによる感覚を「悪寒」と言います。さらに、体熱の産生を増加させるべく、筋肉の収縮(震え)が起こります。この震えを「戦慄」と言います。
従って、発熱初期は体温が上がりきる(設定された体温へ上昇する)まで悪寒・戦慄は続くので、体温計の数値が高くても、保温することが大切です。この時期のクーリングはより寒さを感じさせてしまい、悪寒を助長させてしまうので、行わないようにしましょう。
体温調節中枢が設定したレベルまで体温が上昇してしまうと、高熱にもかかわらず、悪寒や戦慄などの異常感覚は消失します。つまり、正常より高い体温で、体熱の産生と放散の平衡が生まれた状態といえます。身体の火照りを感じるようになったときは、調整レベルに至ったときであり、保温ではなく、クーリングの適応となります。
3)なぜ発熱するのか?
詳しくは分かってませんが、以下のような点から発熱すると考えられています。
病原微生物(ウィルス・細菌など)の増殖が抑えられる
病原微生物であるウイルスや細菌は高温よりも低温で繁殖する特徴があります(ウイルスは約40℃で死滅すると言われています)。つまり、発熱によって体温が上がることで、病原微生物の増殖を抑制することができると考えられています。
免疫応答が活性化する

体内に病原微生物が侵入した際に、免疫細胞が病原微生物を攻撃したり、体を守ろうとさまざまな働きをしたりする反応を免疫応答と呼びます。発熱は免疫応答の活性化にもつながります。例えば、マクロファージといったウイルスを捕食する免疫細胞は、発熱によって一層捕食の働きが強まる傾向にあります。
4)発熱は敵ですか味方ですか?
発熱は、風邪など感染症にかかると出てくる症状であり、辛い症状の一つです。その点からすると、「敵」のようにも感じますが、上述の通り、病原微生物の侵入から体を守る(免疫機能を活性化させる)ために出しているものであるため、むしろ基本的には「味方」と考える方がいいと思います。
そのため、発熱している時は体が熱い割にあまり汗をかきません。ぐずる子供を抱っこしていると子供の肌は乾いているものの、抱っこしている親御さんの方が汗ばんでくるという経験はありませんか?それは、熱を出してる子供は病原微生物から体を守るために熱を上げているので、発熱しているお子さんにとっては大切な熱になるため、汗をかいて熱を下げようとしない一方で、抱っこしている健康な親御さんからすると、抱っこ等を介して発熱している子供から熱が供給されるため、体温が上昇しようとします。しかし、健康な人にとっては、その上昇分は不要な熱であるため、汗をかいて熱を下げようとしているからです。
そのため、時間経過で発熱している子供の状態が改善してくると、体温の設定ポイントを下げるよう指示が出るため、汗をかくことで体温を下げようとします。
5)なぜ朝に熱が下がることが多い?
子供の場合、午後から夜にかけて発熱し、朝になると解熱するため、発熱した時には「明日は病院へ行こう」と思っていても、朝になると解熱し、しかも元気だったりするので、保育園・幼稚園・学校などへ行かせても、発熱で呼出されるという経験をされたことがあると思います。
生活における活動の影響
体温は、朝方がもっとも低く、その後身体を動かしたり、脳を働かせることで、徐々に上昇し、夕方にピークを迎えます。そのため、健康なときに朝と夕方で2回体温を計ると、夕方の方が高くなるのが普通です。なお、病気で発熱したときにも同じような体温の変動が見られます。そのため、「昨日からの熱が、朝は下がっていたのに、夕方にぶり返した」ということが起こります。
体内のホルモンによるもの

炎症がある場合、その抑制のために副腎皮質ホルモン(抗炎症作用など色々な作用があります)が分泌されます。このホルモンの量は、朝から正午にかけて多く、その後減少していきます。そのため、副腎皮質ホルモンの抗炎症作用により炎症が抑えられやすい午前中は熱が下がりやすく、分泌が少なくなる夕方にかけて上昇しやすくなります。
では、発熱に気づいた場合、自宅において、どういう風に対応するのがいいのか次のテーマとして、お話しします。