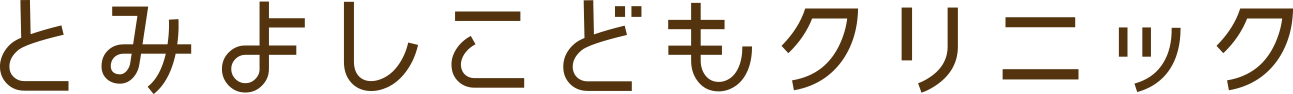こんにちは、とみよしこどもクリニックです。
今日はインフルエンザ検査に関してお知らせです。
インフルエンザの診断については、これまで当院では抗原検査キットを使って行ってきました。
鼻腔に綿棒を入れ、粘液を採取して行う抗原検査の場合、利点としては簡易に行えることや、複数の検査が同時にできるという点があります。(例:COVID-19とインフルエンザの同時検査など)
しかし、コロナ禍になって、発熱することの多い子どもたちにとっては、鼻腔での検査を受ける機会が飛躍的に増えた印象があります。
そのため、診察室=鼻腔検査と覚えている子や、検査前から痛いからイヤと泣く子もいます。
小児科医としては、心苦しく思いながら診断のために検査をしますが、なるべくなら避けたい苦痛です。
この度、この苦痛を少しでも軽減するため、インフルエンザ、COVID-19だけですが、「nodoca」という機器を導入しました。本器は、喉の所見(喉の様子)からインフルエンザ、COVID-19の感染の有無を判定できる医療機器です。
口をしっかり開けて、φ20mm程度の棒状のカメラ(一般的なスティックのりくらいのサイズ)を口腔内に入れて、咽頭後壁(口蓋垂(通称 のどちんこ) の奥)をカメラで撮影(約10枚ほど連続で撮影) ます。その画像からAI がインフルエンザの感染有無を判定します。
撮影後すぐに結果が出るので、抗原検査のように、車などで結果を待つことはなく、診察の流れで結果説明ができます。
(詳細は以下のURL参照。nodoca:https://nodoca.aillis.jp)
当初はインフルエンザのみでしたが、インフルエンザ陰性の判定後、COVID-19についても判定が出るようになりました。
鼻の苦痛を軽減する以外に、早い段階から陽性の判定が出やすい、という事もあります。
一般的に、抗原検査は「24時間くらい経ってないとダメ」というイメージがありますが、nodocaの場合は咽頭後壁の所見の有無を調べるので、感染後の早い段階から所見が出ていれば判定ができることになります。
しかし、以下のような欠点もあります。
(1) えずきやすい人には不向き(「おえっ」となる人)
鼻の検査の痛みも辛いですが、えずく辛さもあります。1 枚でも撮影判定に使えるものがあれば良いのですが、えずいたりして、咽頭後壁がしっかり見える写真が撮影出来ていないと、再撮影となってしまいます。
診察で舌圧子を使って喉を見ることがありますが、nodocaの場合、φ20mmくらいの大きさがあるので、子どもによって鼻腔検査より怖い印象を受けるようです。
(2) COVID-19の判定が3段階
インフルエンザは「陽性」か「陰性」の判定ですが、COVID-19の場合は「陽性」か「陰性」に加えて「判定保留」というものがあります。すなわち、画像ではどちらか判定できないということになるので、白黒はっきりさせるためには、鼻の検査を追加しなくてはならなくなります。
(3) メーカー推奨は6歳以上
臨床試験の段階でメーカーが6歳以上に限定したため、メーカー推奨は「6歳以上」となっています。
咽頭後壁を撮影するには6歳以上の必要性があるとメーカーが設定したので、それ以下の年でできない訳ではありません。
導入して1ヶ月ほどの実績からの意見としては、年齢もそうですが、しっかり口を開けられるかどうかというところがポイントになりそうです。年齢よりは体格もみて使用していきたいと思います。
(4) インフルエンザはA型かB型かわからない
インフルエンザなどの感染でみられる咽頭所見を画像で判定するため、A型・B型の区別ができません。ただA型でもB型でも治療に差はありません。
現在、nodocaを使った診察をスムーズに行うため、発熱外来の6歳以上の子どもには、一律に紙の問診票にも記入して頂いています。(AI が画像で判定する際に必要な情報のみを「はい、いいえ」で回答していただくものになってます。)
6歳未満だが えずかない、などnodocaでの検査に興味がある方は、発熱外来の受付際にお声がけください。(逆に、えずきやすいから、鼻の検査希望の方もお声掛け頂ければ問診票をお渡ししません)
よろしくお願いします。