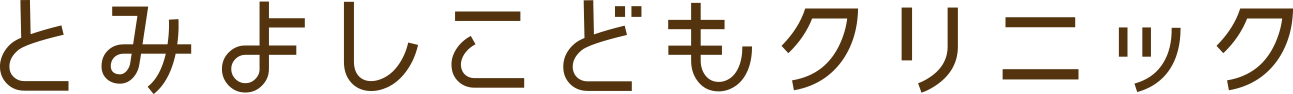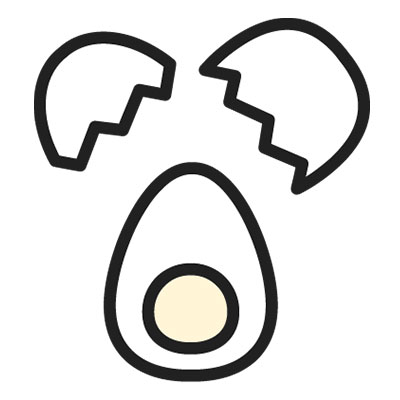
インフルエンザワクチンは、インフルエンザウイルスを鶏の有精卵に注入し、そこで培養・増殖させた後、ウイルス培養液を抽出し、不活化処理を行うという工程で製造されます。
それゆえ、インフルエンザウイルス培養液には、微量の卵由来成分が残存するために、「卵アレルギーがある人は、インフルエンザワクチンを接種できない」と言う話を耳にしたことがあるのではないでしょうか?
実際、ワクチンの添付文書にも、接種要注意者(接種の判断を行うに際し、注意を要する者)のリストの中に、「本剤の成分又は鶏卵、鶏肉、その他鶏由来のものに対してアレルギーを呈するおそれのある者」と明記されています。
インフルエンザワクチンに含まれる卵白蛋白の量は、10ng/mL以下だったという報告があります。(1gの1/1000が1mg、さらにその1/1000が1μg、さらにその1/1000が1ng)
ちなみに、卵白1gに含まれる卵白蛋白(タンパク質)の量は、およそ0.1gです。
仮に1mLのワクチン1瓶の中に10ng含まれているとすると、0.1gの卵白蛋白を取り出すのに、1,000Lのワクチンが必要ということになります。
実際、インフルエンザワクチンで3歳未満は0.25mL、3歳以上は0.5mLなので、接種する量としては、その1/4もしくは1/2となります。

実際に鶏卵アレルギーがある人とない人を比較しても、鶏卵アレルギーがある人の方がアナフィラキシーを起こしやすい訳ではないこともわかっているので、鶏卵アレルギーの重症度に関わらず、通常のワクチン接種の注意以上に追加の予防措置を取らずに接種できる、とされています。
少しでも鶏卵を食べられている場合は通常通り接種できると思われますが、極微量の鶏卵でアナフィラキシーを起こしたことがあるなど心配な場合は、アレルギーを診てもらっているかかりつけの先生に相談の上、接種を検討するといいと思います。
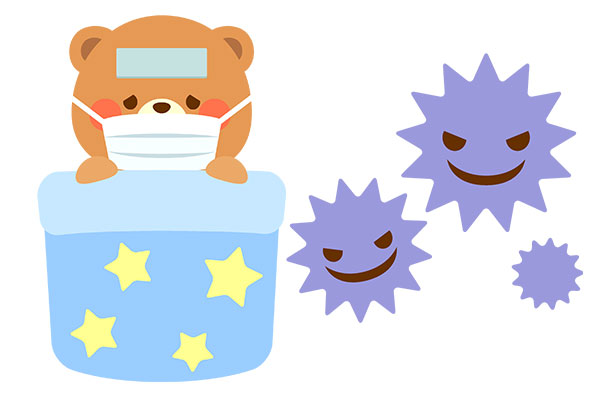
インフルエンザワクチン自身は、発症予防というよりは、重症化予防に比重が置かれています。(特に不活化ワクチン)
通常、インフルエンザに感染すると、1週間程度で回復しますが、感染をきっかけに、肺炎になったり、脳症になったりと重い合併症になる方もいます。
そのインフルエンザの合併症の中でも、最も重い合併症がインフルエンザ脳症です。
死亡率は約30%で、後遺症も約25%の子どもに見られる重篤な疾患です。
なので、インフルエンザワクチンは発症予防も期待しつつ、重症化予防が目的のワクチンと言えます。
ちなみに、小児では、6歳未満の小児を対象とした2015-2016年シーズンの研究では、発病予防に対するインフルエンザワクチンの有効率は約60%と報告されています。
そのため、鶏卵アレルギーを理由に回避して、重症化リスクを負うよりは、接種することで、インフルエンザの重症化を予防していく方が良いと思います。
これまで鶏卵アレルギーを理由として、ワクチン接種を回避していた方も、一度接種を検討して頂けたらと思います。