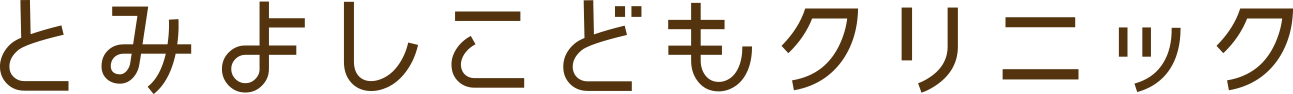目次
熱の出始め

本人が寒気を感じているときは、免疫応答を受け、体温調整中枢が設定した調整レベルまで体温を上昇させるための熱産生中の段階です。その際、皮膚血管の収縮や立毛筋の収縮で体熱の放散量が急速に減少させようとします。その時に生ずる異常な感覚を悪寒(おかん)とよびます。さらに、筋肉の収縮で体熱の産生を増加させようとする反応も起き、このときに生じる震えを戦慄(せんりつ)と呼びます。この悪寒・戦慄を伴って寒気を感じている時は、体温計の数値が高くても、保温が必要です。
体温が上がりきるまで悪寒・戦慄は続くので、この時期のクーリングはより寒さを感じさせてしまい、悪寒を助長させてしまうので、行わないようにしましょう。
熱が上がりきって手足も暖かくなってきた時
悪寒・戦慄を経て、体温調節中枢が設定した調整レベルまで体温が上昇してしまうと、一転して悪寒や戦慄などの異常感覚は消失します。
つまり、正常より高い体温で、体熱の産生と放散の平衡が生まれた状態といえます。この状態になると、状況によりクーリングを行って発熱による不快感を低減させてあげると良いでしょう。
クーリングについて
昔から、発熱時に解熱を目的としてクーリングが積極的に行われていました。しかし、皮膚の上から動脈を冷やしたとしても、全身の体温が下がるという明確な根拠がなく、その有効性は疑問視されています。
しかし、クーリングをするのは、熱を下げることが目的ではありません。発熱による不快感を低減させることが主目的です。クーリングにより「気持ちが良い」と感じることにより副交感神経が優位になり,苦痛の緩和につながる効果が期待できます。従って、元気に過ごせている(しんどそうにしていない)なら、クーリングする必要はありません。
クーリングには、色々なやり方があります。代表的なものは以下の3つくらいです。
- 氷嚢・氷枕・濡れたタオルなどの古典的手法
- 冷えピタ
- 清拭
伝統的な手法が氷嚢・氷枕で頭部を冷やすというもの。しかし、頭部を冷やしたところで、付近に太い血管がある訳でもないため、冷却効果はほぼありません。ですが、冷感を与えることで、「気持ちよさ」を与えられればいいと思います。
ただ、昔ながらの氷嚢や濡れたタオルは上からおでこに乗せる形のため、ズレたときに鼻や口など気道を邪魔する可能性があるという点に注意は必要です。
その点では、氷枕は持続的に冷感を供給できる点で安心ですが、冷たくて眠れないなど逆の不快感を与えるようなら避けたほうがよいでしょう。
最近よく見かける方法としては、冷えピタを貼ることかと思います。
おでこに貼ってる姿は病院などで見かけたことがあると思いますが、診察室では背中や脇などに貼ってる姿もたまに見かけます。
確かに貼ることで冷たさを感じますが、ジェルに含まれている水分が蒸発することによる「気化熱」によって、貼付部の温度が局所的に下がることを期待してます。これは貼付部の局所的な温度であり、体温を下げるまでの効果は期待できません。ただ他のクーリング手法と同じで、「気持ちが良い」と感じることにより副交感神経が優位になり,苦痛の緩和につながる効果は期待できます。
しかし、氷嚢やタオルと異なり、粘着物質による貼り付けになりますので、特に就寝中のおでこに貼ってると、ズレたりなど予期せぬハプニングにより鼻や口など気道を閉塞する事故が起こる可能性があるという点に注意は必要です。
また子供、特に乳児だとおでこに貼られたりすることを嫌がることがあります。その場合は、無理に貼り続けようとするより、次に述べる清拭にて肌を濡らしてあげる方が良いかもしれません。
清拭は、冷却という点では効果は弱そうですが、濡れたタオルで全身を綺麗に拭きつつ、多少肌を湿らせることで、その水分が蒸発する際の気化熱による冷感を得るという手法です。
ただ肌を濡らす水分量が少ないため、他の手法に比べると冷感が得られにくいかもしれません。
ただ乳幼児の場合、保護者の方から清拭をされることによる安心感や、リスクがない事に加え、肌を清潔にすることもできます。

解熱剤について
発熱について述べた時に書きましたが、熱は下げなければならないものではありません。
では、解熱剤は使わない方がいいのか?というと、これに対する正解はないと思います。
使わないことで、高熱が続き、辛い症状が続くことで、食事・水分摂取が減ったり、しっかりとした睡眠が取れず、体力を回復させられない。結果として、病気から回復がスムーズにいかない可能性が高まります。
では、解熱剤を使えばいいのかというと、免疫機能を活性化させ、病原微生物の増殖を抑制するために上げた熱を下げるということは、免疫機能が少し低下し、病原微生物の増殖を抑制しにくくなるということになり、結果的には、病気からの回復がスムーズにいかないというストーリーになります。
結論としては、安易に解熱剤を使って熱を下げるのではなく、安眠できないとか、食事や水分摂取がままならない場合には積極的に使用し、それなりに食事や水分摂取ができる状況であれば、解熱剤の使用よりも積極的なクーリングをしながら、子どもの状態を観察するのが良いと思います。
経口摂取について
発熱して体調悪い時に、これを摂取すればいいというものはありません。
色々調べると、タンパク質やビタミンCなどが取り上げられたりしてますが、発熱していることで、食欲不振になっていることが多いので、「食べれるものを食べる」というのが、メインになると思います。

そして何より大切なのは、水分摂取です。
普通に過ごしているだけでも、不感蒸泄という皮膚や呼吸からの自然な水分の蒸発により喪失する水分量(排尿込み)があり、小児の場合、1日あたり約80~90ml/kgと言われています。
つまり普通に生活するだけで、体重10kgのお子さんは800~900mlの水分を自然に喪失していることになります。
言い換えると最低でもその量くらいは水分摂取していかないと摂取量が少ないことになります。
それが発熱している状況では、不完蒸泄が約15%ほど増加するとされるので、体重10kgのお子さんは900~1000mlの水分を自然に喪失することになるため、いつも以上に水分摂取が必要ということになります。
日常生活では、飲水の他に、食事摂取からも水分を摂取していることになるので、摂取水分が少ないということはほぼほぼないと思いますが、発熱など体調不良があると、水分摂取に繋がる経口摂取(食事・飲水)自体が少なくなるため、より意識して水分を摂取していかないと脱水方向に体が傾いていくことになります。
昔から、「食べないと元気にならない」などという言葉を耳にしますが、正しくは「飲まないと元気じゃなくなる」というのかもしれません。
入浴について
基本的には、熱が高い時の入浴は控えた方がいいというのが一般的です。
特に湯船に浸かるという行為は、体力をかなり消耗します。ただでさえ、発熱して体調不良により体力的に落ちている状態だと、入浴そのもので更に体力を低下させたり、脱水を加速させたりと、健康上のリスクになるというのがその理由です。
ただ、お風呂(入浴)といっても、2種類あると思います。一つは、いつものお風呂。つまり、湯船にゆっくり浸かって、体をリラックスさせたり、子供の場合はお風呂ならではのおもちゃを使って遊びながら、体を洗ったりするお風呂。
もう一つは、体を綺麗にするだけのお風呂(いわゆるシャワー浴)。この場合、湯船に浸からないので、体力消耗は最低限に済ませられます。
子供の場合、比較的熱が高くても元気に動けることも少なくないので、元気と思えるようなら、体を綺麗にするためのお風呂はありだと思います。
特に乳幼児はオムツで生活しており、いくらお尻拭きなどでこまめに綺麗にしていても、お風呂でしっかり水分を使って綺麗にすることに勝るものはありません。更には、子供は新陳代謝が活発なため、大人と比較して垢が出やすかったり、汗をかきやすかったりするため、特有の問題が発生することがあります。
そのため、1日お風呂で体を綺麗にしないだけで本人の不快感は増してしまいます。入らなければいけないものではありませんが、入れそうなら入るのが良いと思います。
熱性痙攣について

生後6か月~5、6歳の子供(小学生未満の子供)が38℃以上の発熱により、発作的に起こる疾患で、他に痙攣を症状として起こしやすい疾患ではないものを言います。
基本的には、5分以内に痙攣は頓挫(止まる)ことが多いため、「救急要請せずに様子みてください」というような記載がされていることが多いですが、初めての痙攣の場合や、これまでに痙攣したことあるがその時とは明らかに様子が違うという場合は、救急要請した方が良いと思います。
熱性痙攣の症状
- 両手足・背中をかたく突っ張った後に、両手足をガクガクふるわせる(突っ張ったままということもあります)
- 意識がなくなる。それにより、呼びかけても反応なく、呼吸もしていないことが多いため、顔色が悪くなり、口唇にチアノーゼが出現することがあります。
- 白目をむく(眼球上転)。目の焦点が合っていないように見える。
- 嘔吐や失禁を伴うこともある。